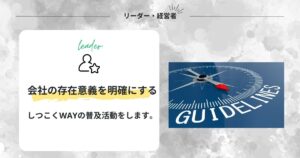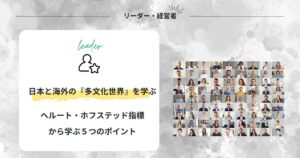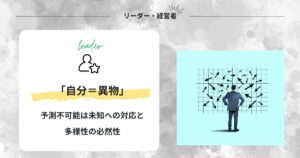2019年6月
管理職が率先垂範すべき3つの行動
2019年6月10日
こんにちは! 部下とのお悩み解決専門家、谷口彰です。 企業研修をしていると、「率先垂範」についてのご質問を多く受けます。 皆さん、自分は組織において、部下に対して、どのような姿勢を見せればよいのか? という悩 […]
部下に違和感を感じたら、今がチャンスです
2019年6月7日
2019年6月7日 Vol.025 「違和感を感じたときがチャンス」についてです。 会社で部下、同僚・上司にたいして、『違和感・ザワザワ感・モヤモヤ感』を感じたときは、自分が変革する「チャンス」です。 例えば・・・ なぜ […]
ビジョンを明確にする
2019年6月6日
2019年6月6日 Vol.024 「会社のビジョン」についてです。 こんにちは、谷口彰です。 昨日のブログで、「会社の存在意義を明確にする」を書きました。 よく本でも雑誌でも、ビジョンを持つ、ビジョンを作る、戦略はビジ […]
会社の存在意義を明確にする
2019年6月4日
2019年6月5日 Vol.023 「会社の存在意義」についてです。 こんにちは、谷口彰です。 会社はなぜ存在するのでしょうか? 会社の役割と意義は? 社会的存在は? 企業活動とはなに? などなど、色々な質 […]
ヘルート・ホフステッド指標から学ぶ5つのポイント
2019年6月4日
2019年6月4日 Vol.023 「日本と海外の『多文化世界』を学ぶ」についてです。 こんにちは、谷口彰です。 海外で働いていると、ヘルート・ホフステッド指標をよく目にします。これはオランダの「ヘルート・ホフステッド」 […]
予測不可能は未知への対応と多様性の必然性
2019年6月3日
2019年6月3日 Vol.022 「多様性の必然」についてです。 こんにちは、谷口彰です。 海外(今はインドです)で働いていると、当然インド人と日本人の考え方の違いに悩みます。これは当たり前のことで、言葉と歴史、食べ物 […]